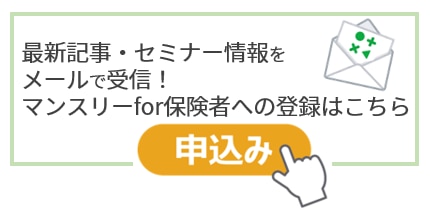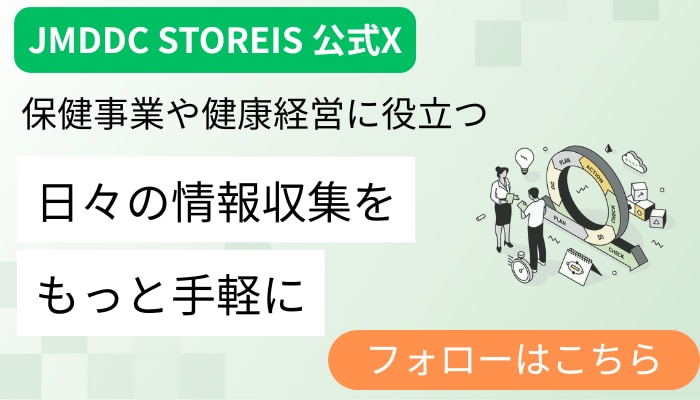保険者向け|フレイル・サルコペニアとは? 要介護を防ぐための対策ポイントを整理
「要介護状態の一歩手前」であるフレイル、およびサルコペニア。近年その有症率は増加傾向にあり、国が策定する「健康寿命延伸プラン」でも、フレイル予防を重要な柱のひとつとして位置づけています。
そんな社会問題にもなっているフレイル、サルコペニアは、健康診断で早期にリスクを把握したり、保健事業で生活習慣の見直しをサポートしたりすることで予防や改善を図れます。
そこで今回は、フレイル、サルコペニアの基礎知識と、保険者ができる具体的な対策をご紹介します。
3つの側面からなる「フレイル」とは?
フレイルの語源は、虚弱を意味する「Frailty(フレイルティ)」。その由来のとおり「おもに加齢が原因で心身が虚弱の状態にあり、運動や認知の機能に問題が生じていること」を指します。
そんなフレイルは、日本老年医学会によると、身体的・精神的・社会的要素の3側面からなると定義されています。
- 身体的要素:サルコペニア、ロコモティブシンドローム など
- 精神的要素:うつ、認知機能や意欲の低下 など
- 社会的要素:社会とのつながりの希薄化、独居、経済的困窮、孤食 など
上記3つの要素はお互い密接に関係しているため、いずれかに当てはまると連鎖的に該当範囲が広がり、急激に健康状態が悪化してしまう場合もあるといわれています。例えば、筋肉の衰えによって外出のハードルが上がると閉じこもりにつながり、人と会う機会がどんどん減少するといった具合です。
なお、フレイルは決して高齢者だけの問題ではありません。心身の機能はあるとき突然低下するわけではなく、加齢や生活習慣の乱れなどによって徐々に衰えていくもの。日本整形外科学会による調査では、働き盛りの40代から移動機能の低下(ロコモティブシンドロームの進行)が加速するという結果が出ています。
フレイルの身体的要素①「サルコペニア」
フレイル3要素のうち身体的要素に分類される「サルコペニア(筋肉減弱症)」は、筋肉量の減少や筋力の低下を指します。進行すると、立つ、歩くといった日常動作が困難になったり、転倒リスクが高まったりする恐れがあります。おもな原因は栄養や運動量の不足で、特に痩せ型の方に多く見られるのが特徴です。
フレイルの身体的要素②「ロコモティブシンドローム」
筋肉量の低下や骨、関節の疾患などが原因で運動器に障害が起こり、移動機能に支障をきたしている状態を指します。つまり、サルコペニアはロコモティブシンドロームに含まれる概念です。
保険者にできるフレイル対策
フレイルやサルコペニアの予防、改善にあたっては、ご紹介した3つの要素すべてを意識した対策が必要になります。根幹となるのは、「運動によって筋肉の維持や向上、肥満の解消を図ること」「社会参加により人とのつながりをつくること」「栄養バランスに配慮しながら食事を必要量とること」です。
これをふまえ、保険者ができるフレイル対策のための保健事業としては、運動習慣の定着や人とのつながりづくりに役立つ「ウォーキングイベント」、生活習慣の改善や社会参加へのヒントを得られる「セミナー、コラムなどによる情報提供」などが挙げられます。
そのほか、自治体や地域包括支援センターと連携して施策を展開する方法も。支援の質を高めるだけでなく、地域包括ケアシステムの構築、マネジメントという「保険者に近年求められている役割」を果たすことにもつながるでしょう。
なお、フレイル対策は、保健事業実施率や地域連携などの評価指標との親和性が高いのもポイント。多角的に見てメリットの大きい取り組みといえます。
・早期のリスク把握、対策スタートも重要なポイント
保険者ができる対策として、若いうちからの健診や保健指導による早期のフレイルリスク把握も挙げられます。フレイル予備軍のことを「プレフレイル」と呼びますが、330名の整形外科医や産業医にヒアリングした日本生活習慣病予防協会の調査では、75.5%の医師が現役世代でプレフレイルが増加していると回答しました。働き盛りの年代にも、フレイルの可能性を考慮した健康チェックが求められています。
また、高齢になってからいきなり運動や食事などの生活習慣の見直しや社会とのつながりづくりに取り組むこと、またフレイルが進行してから健康状態の改善を目指すことはなかなか難しいもの。高齢者になる前からフレイル、サルコペニアについて理解を深め、きちんと意識しておくことで、予防効果を高められるといえます。そのため、保険者による現役世代に向けた働きかけは、フレイル対策において非常に重要な意味をもつのです。
フレイル対策で保険者機能のさらなる向上を
要介護の前兆であるフレイルやサルコペニアは、保険者が適切な対策を講じることで予防、改善を目指せます。
こうした取り組みは、総合評価指標大項目7「加入者に向けた予防・健康づくりの働きかけ」小項目⑪「ロコモティブシンドローム対策」にも該当し、介護予防や健康寿命の延伸という社会目標に大きく寄与するものです。
ぜひ保険者だからこそできる「先回りの対応」でフレイルの予防、改善を図り、保険者機能のさらなる向上を目指してください。まずは、現段階で無理なくできる施策から始めてみてはいかがでしょうか?