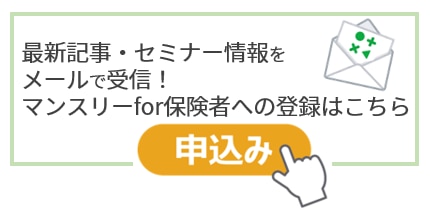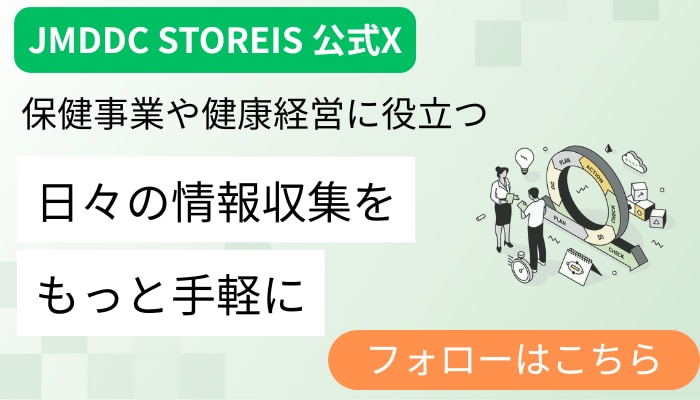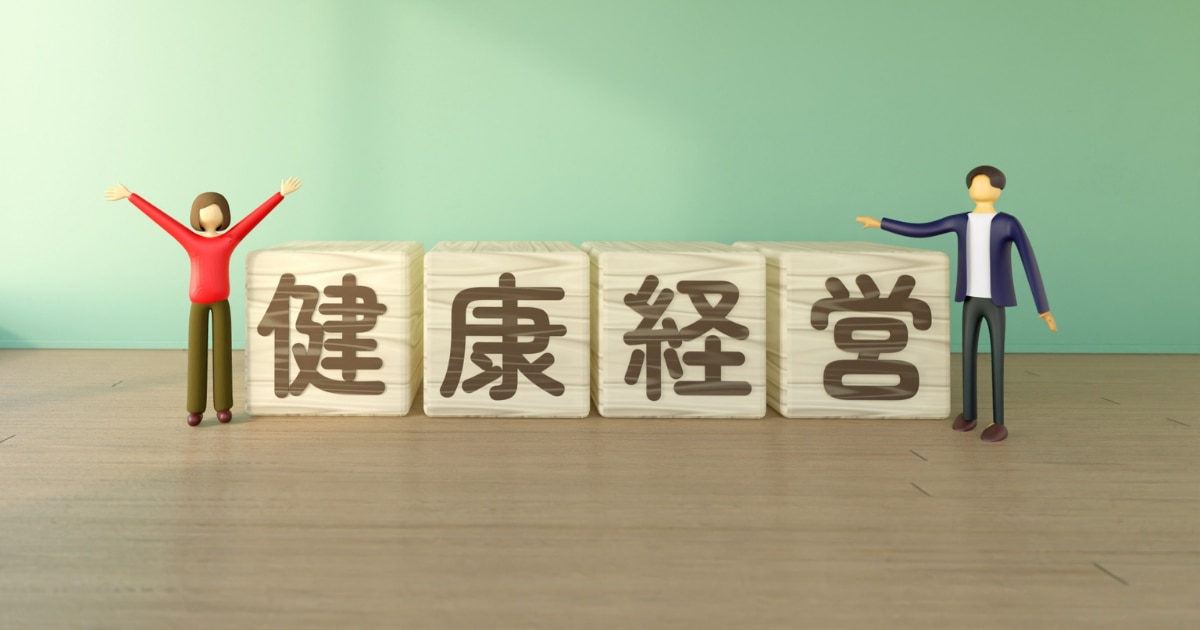
【記事まとめ】保険者のための健康経営|基礎から実践・データ活用を解説
健康経営は、従業員や加入者の健康を守りながら、企業の生産性向上や健保財政の持続可能性にもつながる取り組みとして注目を集めています。保険者にとっても、制度対応や事業主との連携を進めるうえで欠かせないテーマです。
本記事では、JMDC STORIESでこれまでご紹介してきた記事に加え、健康経営アライアンス「トップインタビュー」に掲載された外部情報もまとめました。
基礎知識から、コラボヘルスの実践方法、データ活用、最新の制度改訂ポイント、そしてJMDC代表 野口が語る、データを活用した健康経営推進の視点まで──健康経営の全体像を理解できる記事となっています。ぜひ今後の保健事業の企画や事業主との協働にお役立てください。
健康経営の基本をおさらい!認定に向けて保険者が協力できること
少子高齢化や人的資本経営の流れを背景に、「健康経営優良法人」認定への注目が高まっています。制度の理解や申請スケジュールを把握することはもちろん、事業主の取り組みを保険者がどうサポートできるかが重要なポイントです。
本記事では、認定制度の仕組みやメリットを整理しつつ、データの共同利用や健康宣言事業への支援など、保険者が実際に協力できるアクションを具体的に解説。事業主との連携を深め、施策の実効性を高めたい保険者にとって必読の内容です。
▼記事はこちら
コラボヘルスとは?データヘルス、健康経営の相乗効果を発揮するポイントと注意点
保険者のデータ分析力と、事業主の健康経営の取り組みを組み合わせる「コラボヘルス」は、加入者の健康増進を実現するための有効なアプローチです。しかし、実際に進めるには、推進体制の整備や現状把握、共通指標の設定など、いくつものハードルがあります。
本記事では、コラボヘルスの基本的な考え方から、成功に導くための具体的なステップ、さらに個人情報の取り扱いにおける注意点まで幅広く解説。データヘルスと健康経営の相乗効果を引き出すためのヒントが詰まっており、これからコラボヘルスを本格化したい保険者に役立ちます。
▼記事はこちら
健康スコアリングレポートとは?スコアの見方とコラボヘルスでの活用方法
健康スコアリングレポートは、健保の加入者の健康状態や医療費を可視化する公的レポートであり、事業主と共通認識を持つための重要なコミュニケーションツールです。レポートの活用により、特定健診・特定保健指導などの協力を得やすくなり、事業主の意識を高める効果が期待できます。
本記事では、スコアリングレポートの見方や種類を整理し、実際にコラボヘルスに活用された事例を紹介。レポートでカバーしきれない部分を補う方法にも触れており、保険者が「レポートをどう使いこなすか」を具体的にイメージできる内容です。
▼記事はこちら
【速報解説】令和7年度 健康経営度調査票が公開!改訂ポイントとは?セミナーレポート
2025年8月18日に公開された令和7年度版 健康経営度調査票。健康経営優良法人認定にも関わる重要な制度であり、保険者にとって注目すべき改訂が含まれています。
本記事では、JMDCが開催した速報解説セミナーの内容をもとに、昨年度からの主な改訂点や保険者が特に押さえておきたい3つの設問(PHRデータ活用、女性特有の健康課題、従業員の健康保持・増進施策)を整理。さらに、施策を検討するうえで重要な3つの視点(基本的対策・土台づくり・具体的対策)も解説しています。
制度対応を迫られる保険者にとって、改訂の方向性を早くつかみ、実務に反映するためのヒントとなる記事です。
▼記事はこちら
【掲載情報】健康経営トップインタビュー
JMDC代表 野口亮が語る、データドリブンな健康経営
健康経営アライアンス(※)の公式サイトで公開された「トップインタビュー」に、JMDC代表取締役社長CEO 野口亮が登場しました。インタビューでは、自社ビジョン「健康で豊かな人生をすべての人に」を起点に、社員自身の健康を守ることの重要性、そしてデータを活用した健康経営のあり方について語っています。
具体的には、ストレスチェックやパルスサーベイを活用して課題を可視化し、PDCAを回す仕組みを整えていること、さらにポイントインセンティブ制度を取り入れて社員の行動変容を促していることを紹介。ウォーキングイベントや「ウェルネスアンバサダー」制度など、現場を巻き込みながら健康づくりを推進する仕組みも取り上げられています。
こうした取り組みを通じて、社員一人ひとりの健康意識を高めるだけでなく、保険者や企業と連携しながら社会全体の健康経営の発展に寄与していく姿勢を示しています。
健康経営アライアンスのサイトでは、JMDC以外にもさまざまな企業・団体のトップが自社の取り組みを語っています。複数のインタビューを見比べることで、それぞれのアプローチや工夫を知ることができ、保健事業や連携のヒントになるはずです。
※健康経営アライアンス https://kenkokeiei-alliance.com/
2023年6月、味の素株式会社、SCSK株式会社、オムロン株式会社、キリンホールディングス株式会社、株式会社島津製作所、株式会社JMDC、日本生命保険相互会社、株式会社野村総合研究所、株式会社三井住友銀行(50音順)が代表幹事となり設立された団体です。
「社員の健康をつうじた日本企業の活性化と健保の持続可能性の実現」をミッションに掲げ、498の企業・団体が参画しています(2025年8月28日現在)。
▼インタビュー動画はこちら(健康経営アライアンス公式サイト)
健康経営の最新動向と保健事業への活かし方
健康経営は、制度対応としての重要性はもちろん、加入者・従業員の健康を守り、組織の活力や健保財政の持続可能性につなげるための大きなテーマです。
本記事でご紹介した各記事には、制度の基本からコラボヘルスの実践、データ活用、最新動向やトップの視点まで、幅広い情報が詰まっています。
保険者にとっては、これらを組み合わせて 「事業主との連携をどう深めるか」「データをどう活用するか」 を考えることが、今後の保健事業を進めるうえでますます重要になります。
ぜひ各記事を参考に、健康経営の最新動向を踏まえた保健事業の企画・実践にお役立てください。